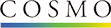「企業は社会の公器である」と言われます。企業を取り巻くステークホルダーは多様化しており、企業には、社会から実に様々な要請が課されるようになりました。それに伴って、社会からの注目もますます高まっています。
「生活者が『企業の果たす役割・責務』と考えていることは何か」-と聞いた最近の調査(1)によれば、1位は、「安全・安心で優れた商品・サービス・技術を適切な価格で提供(78%)」、2位は「不測の事態が発生した際に、的確な対応を取る(59%)」、3位は「社会倫理に則した企業倫理を確立・順守する(56%)」であったという結果が紹介されています。これら上位3項目は、一見何の関係もなさそうですが、実は相互に密接不可分に関連する事柄であり、多くの実例が示す通り、これらの期待に応えられない企業は、社会からの厳しい批判にさらされることになります。
メディアの影響力と企業広報の役割
日本でのメディア対応は思っている以上に複雑で、関係構築やタイミングが重要になります。その影響力を最大限に活かすためには、メディアの特性を理解し、適切なコミュニケーションを行うための準備が不可欠です。
日本では、SNSやニュースアプリといったデジタルメディアの台頭が著しいものの、テレビ、新聞、雑誌といった従来のメディアも依然として大きな影響力を持っています。
長年培われた信頼と情報収集力、幅広い伝達力を持つ従来のメディアは、特に中高年層や地方において、依然として重要な情報源としての地位を確立しています。企業や行政機関にとっては、広範な層への情報伝達やブランドイメージの構築において、今でもなお無視できない存在です。特にテレビは、視聴率の高い番組による情報の拡散や世論形成に大きな役割を果たしています。また、新聞は信頼性のある情報源として根強い読者層を持ち、政治や経済に対する影響力も無視できません。一方で、SNSやニュースアプリは、若年層を中心に速報性や双方向性を強みとし、情報拡散のスピードと範囲を飛躍的に拡大させています。
さらに、日本特有のメディア環境は、情報発信者にとって独特の課題ももたらします。例えば、記者クラブ制度、横並び意識、そして「空気を読む」文化など、海外とは異なるメディアの慣習や価値観が存在します。これらの要素を理解せずに情報発信を行うと、意図せぬ誤解や炎上を招きかねません。さらに、デジタルメディアと従来のメディアの連携が進む中、情報の正確性や信頼性に対する意識も高まっています。
社内の広報人材をいかに育てるか
企業広報は、社会に向かって開かれた情報の窓口として、企業の透明性を高め、説明責任を果たす重要な役割を担っています。その企業広報活動の中で大きなウエイトを占めているのが、メディアを通じた情報発信です。ニュースリリースの配信、記者発表会、記者会見、個別の取材協力、インタビューなど様々なケースが想定されますが、これらの企画・立案に当たっては、①実現すべき目標や到達すべきゴール、②ターゲット、③発信すべきメッセージやストーリーを明確にするなど、綿密な準備が必要です。自社が社会に提供する商品、サービス、技術の優位性をはじめ、自社の持つ強みを洗い出す作業も欠かせません。
一方で、「メディアは今、何に関心を示し、どんな情報に反応するのか」や、「社会は今、何に関心を寄せているのか」など、常に情報のアンテナを高く張り巡らせて、自社の広報戦略にフィードバックさせることも必要不可欠です。また、全国紙の記者、地方紙の記者、専門紙の記者、雑誌・週刊誌の記者、TVのリポーター、フリーランスのジャーナリストなど、あらゆるタイプのメディアの人々と的確にやり取り出来るコミュニケーション・スキルも求められます。
これらの企業広報に求められる能力、スキルを私たちはどのように培い、どのように人材を育てればよいのでしょうか。
これまで多くの企業では、長い年月をかけて実践と経験を積み重ね、社内人材を養成し、社内における広報体制を一歩一歩構築してきました。しかも、社会から厳しい批判を受けた企業ほど、その不幸な経験や失敗を貴重な糧として、広報体制を強化・充実させ、今の高い評価を得るに至っていることは歴史的な事実です。しかし、企業間の競争がますます激しさを増す今日、現実に失敗を繰り返しながら広報の力をつけていくというようなリスクを冒すことはもはや許されません。
これからはリスクを冒すことなく、日頃からシミュレーションを繰り返し、スキルを身に着け、社内の広報人材を育成していく必要があり、これこそが「メディアトレーニング」なのです。そしてその「メディアトレーニング」の対象は、広報部門に限りません。むしろ、普段メディアとの接触の頻度の少ない企業トップや各部門の責任者が自ら率先して訓練を受けることで、全社を挙げた広報支援体制を構築すべきでしょう。
コスモが提供するメディアトレーニングとは
コスモが提供するメディアトレーニングは、先に触れたような日本特有のメディア環境を踏まえ、最適なコミュニケーション戦略を構築するための実践的なトレーニングで、単なる「話す練習」ではありません。
日本のメディア環境の理解から、メディア関係者との良好な関係構築、メディアが重視する視点や表現方法(ボディランゲージや話し方)、さらには、組織のキーメッセージを的確に伝えるスキル、想定される質問への回答準備まで、幅広くカバーします。メディアと向き合う機会では、しばしば厳しい質問を受けるため、想定外の質問にも落ち着いて対応できる能力が不可欠です。しかも、広報におけるメディア対応では、広告と違い、記事の事前チェックはできません。
メディアトレーニングでは、こうした状況を想定した模擬インタビューやロールプレイングを通して、実践的なスキルを習得することができます。的確なメッセージを伝え、自身のブランドイメージを効果的に構築するための戦略的なスキル習得の場です。
情報過多な現代において、誤った情報や不適切な表現は、企業や個人の評判を大きく損なう可能性があります。リスクを回避し、チャンスを最大限に活かすために、メディアトレーニングは必要不可欠な投資と言えるでしょう。「センス」は生まれ持った感性やひらめきなどによるところが大きいと言われていますが、「スキル」は学習や訓練によって確実に向上させることが出来、具体的な行動や成果に結びつけることを可能にします。広報体制の見直しや強化を図る際には、メディアトレーニングの重要性を再認識し、取り組むことをお薦めします。
コスモのメディアトレーニングについて、さらに詳しくお知りになりたい方は、こちらからお問い合わせください。なお、本稿では、「平時」のメディアトレーニングを取り上げましたが、コスモでは「緊急時の広報対応」を想定したメディアトレーニングも提供していますので、合わせてお問い合わせください。
■参考文献
https://www.kkc.or.jp/release/?mode=show&id=191/